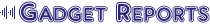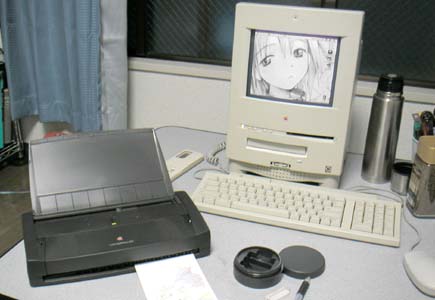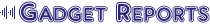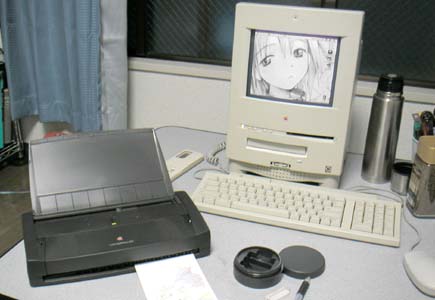| 端子 | 信号名 |
|---|
| 1 | +12V |
| 3 | +5V |
| 5 | +5V コントロール |
| 7 | パワーオン信号(負論理) |
| 9 | コンポジット/水平同期信号 |
| 11 | ビデオ信号 青 |
| 13 | ビデオ信号 緑 |
| 15 | ビデオ信号 赤 |
| 17 | 輝度 |
| 19 | コントラスト |
| 21 | マイク入力 (+) |
| 23 | +5V |
| 25 | モニターセンス ID 0 |
| 27 | N/C |
| 29 | 右音声出力 - |
| 31 | 左音声出力 - |
| 33 | 垂直同期信号 |
| 35 | N/C |
| 37 | 内蔵アンプミュート |
| 39 | CRT省電力制御 |
| 41 | N/C |
| 43 | N/C |
| 45 | GND |
| 47 | GND |
| 49 | GND |
|
| 端子 | 信号名 |
|---|
| 2 | GND |
| 4 | GND |
| 6 | GND |
| 8 | GND |
| 10 | GND |
| 12 | GND |
| 14 | GND |
| 16 | GND |
| 18 | GND |
| 20 | モニターセンス ID 2 |
| 22 | マイク入力 (-) |
| 24 | モニターセンス ID 1 |
| 26 | GND |
| 28 | 右音声出力 + |
| 30 | 左音声出力 + |
| 32 | GND |
| 34 | N/C |
| 36 | GND |
| 38 | GND |
| 40 | GND |
| 42 | N/C |
| 44 | CD-ROM 左音声入力 + |
| 46 | CD-ROM 左音声入力 - |
| 48 | CD-ROM 右音声入力 + |
| 50 | CD-ROM 右音声入力 - |
|